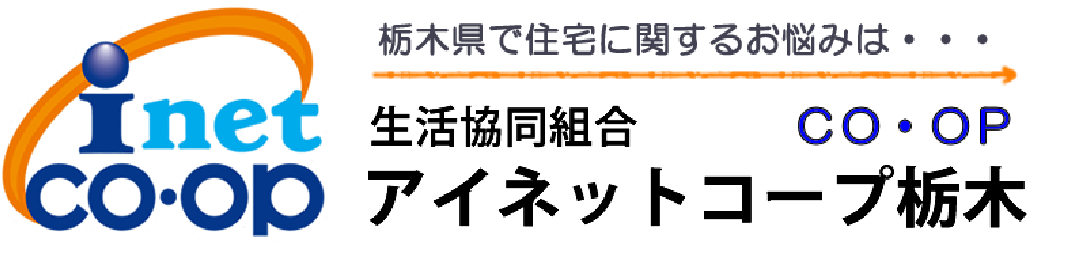お知らせ News/Column
シロアリとの長い戦い:日本の住宅と共に歩んだ歴史
2025年06月25日 [塗装・シロアリコラム]

1.歴史に刻まれた”シロアリ” – 奈良時代からの住宅リスク
日本最古のシロアリ被害記録
日本では奈良時代(710–794年)から木造建築が主流となり、この時期にはすでにシロアリ被害が発生していました。『大日本古文書』などの古文書には、木材が「中空化」する現象や「木が白くなる」症状が記録されており、当時からシロアリが深刻な住宅リスクとして認識されていたことがわかります。
古代建築に学ぶ防蟻の知恵
奈良時代の寺社建築では、シロアリ対策として以下の工夫が施されていました。
• 礎石高床構造:地面と木材を切り離し、湿気やシロアリの侵入を防止
• ヒノキ材の活用:天然の耐蟻性を持つヒノキを構造材に使用
• 高床設計:床下の通気性を確保し、湿気を抑制
これらの技術は、自然の力を最大限に活かした合理的な防蟻策として機能していました。
2.避けたいNG習慣 – 歴史から学ぶ「やってはいけない家の管理法」

江戸時代に学ぶ危険な管理法
江戸時代の記録によると、「土間・湿気・放置」は最も危険な住宅管理法として警戒されていました。土間に湿気が蓄積すると木材が腐朽し、シロアリの格好の繁殖場所となってしまいます。
現代でも変わらないリスク要因
現代の住宅でも、以下のような習慣はシロアリを誘引する大きなリスクとなります
• 床下換気の不足
• 換気扇の故障を放置
• 水回りの水漏れを放置
• 湿気対策の怠り
「換気扇の故障に気づかず数ヶ月放置していた」という事例は決して珍しくありません。湿気を溜める生活習慣は、シロアリを呼び込む最大の要因であることを認識しましょう。
3.技術と生活のアップデート – 江戸〜近代の進化する防蟻対策

江戸時代の自然素材対策
江戸時代には、自然由来の材料を使った防蟻対策が発達しました。
• 焼き土台:木材を焼いて耐久性を向上
• 塩・灰の散布:天然の防虫効果を活用
• 鯨油の塗布:礎石に塗ることで防蟻効果を期待
これらの技術は環境に優しく、当時の人々の知恵が詰まった対策法でした。
近代以降の化学薬剤の登場
昭和期に入ると、化学薬剤による防蟻対策が本格化しました。
• DDTの導入:画期的な殺虫効果を発揮
• 除虫菊・ピレスロイド系薬剤:より安全性の高い薬剤の普及
• バリア工法の確立:薬剤による土壌処理技術の発展
これらの技術革新により、シロアリ駆除はより効果的になりましたが、同時に環境への影響も課題となりました。
4.今だからできる!実践すべき”今日から始める”予防ポイント
現代の住宅でも、歴史に学んだ知恵を活かすことで効果的なシロアリ対策が可能です。

具体的な実践ポイント
木材選びの工夫
• シロアリに強いヒノキ材の使用
• 防蟻処理済み木材の選択
• 薬剤注入材の活用
湿気対策の徹底
• 床下換気の定期点検
• 換気扇のメンテナンス
• 水回りの点検・修理
専門的な予防措置
• 年1回の専門家による点検
• 必要に応じたバリア工法(薬剤注入)の実施
• 早期発見・早期対処の徹底
これらの対策を継続することで、「シロアリが発生してから慌てる」という事態を防ぐことができます。
まとめ:シロアリとの”長い戦い”から得る、今日の安心住宅づくり
奈良時代の高床構造とヒノキ材の活用、江戸時代の焼き土台や天然素材の利用、近代の化学薬剤による防除技術—これらすべての知恵が、現代の安心住宅づくりの基盤となっています。
本記事では、各時代の防蟻対策の変遷を整理し、現代でも実践可能な具体的な対策をご紹介しました。少しの工夫で大きな安心を得られる住宅づくりの参考にしていただければ幸いです。
歴史に学び、現代の技術と組み合わせることで、シロアリに負けない住まいを実現しましょう。
気になることがありましたら、お気軽にご相談ください。
生活協同組合アイネットコープ栃木
フリーダイヤル:0120-934-124